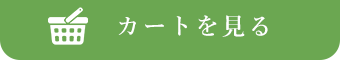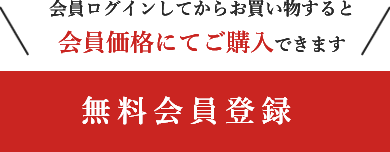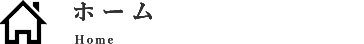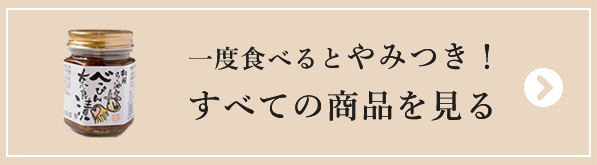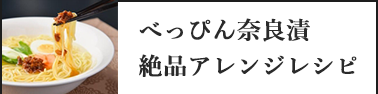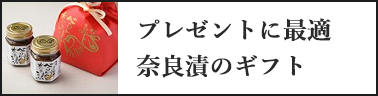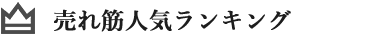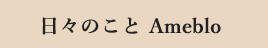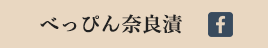戦国武将を支えた兵糧
石垣奈良漬
『石垣に宿る、武将の知恵と奈良の味』
「豊臣秀吉公・秀長公 兄弟ゆかりの地・奈良から生まれた、『石垣奈良漬 × 戦国めし』 奈良の歴史と発酵文化を、現代の“手に取れるお土産”としてカタチにしました。豊臣秀吉の弟・秀長は、大和一円を治める拠点として郡山城を大改修しました。
その規模は約60万石、当時は大坂城・聚楽第に次ぐ西日本有数の巨城とされます。
壮大な石垣と堀は堅牢さの象徴であり、城下町には寺社を移して町を整備。奈良の政治・経済の中心地として繁栄しました。
一方で、戦国の兵糧は勝敗を分ける命綱。干飯(ほしいい)、梅干し、味噌玉と並び、酒粕漬けの野菜も保存食として兵を支えました。
現代の石垣奈良漬は、その「兵を支える兵糧」と「城を守る石垣」をかけ合わせた奈良の物語です。
郡山城を築いた豊臣秀長は、寺社仏閣を含む各地から集めた石碑や仏像を“寄せ集め”、強固な石垣を築いたといわれています。
それは、バラバラだった力をひとつにまとめ、町と人を守る「知恵の結晶」。
奈良の伝統食“奈良漬”を乾燥させ、歯ごたえとコクを閉じ込めた一粒は、
まるで一つひとつの石のように、力強く、深い味わい。
『戦国武士を支えた兵糧 ― 奈良漬と武将の知恵』
長い戦を生き抜くため、戦国武将たちは「兵糧(ひょうろう)」=携帯保存食を常に携えていました。
干飯(ほしいい)や味噌玉、そして**保存性に優れた“酒粕漬け”**もその一つとされます。
とくに奈良は古くから酒造りが盛んで、副産物である酒粕を活かした野菜の漬物が重宝されていました。
この発酵の知恵と保存力、わずかな量で力になる“兵糧”は、まさに戦国の知恵の詰まった味。
石垣奈良漬けは漬け込みの酒粕を取り除いて天候・気温・湿度をみながら丁寧に乾燥しております。
本来の3分の1までに乾燥していますのでお口に含むとどんどん旨味と甘味が広がっていきます。
現代では、熱中症対策のひとつとしてご愛用いただくことも。
時代を越えて、発酵の恵みが人々の力になってきたことに、深い喜びを感じています。
戦国めしシリーズ

石垣奈良漬と並ぶ“戦国めしシリーズ” コンセプトは『兵糧の知恵 と 戦国時代』。 秀長公が築いた“つなぐ力”を軸に、秀長公とゆかりの武将たちの個性を それぞれの味にリンクさせた “歴史体験型”のごはんのお供としました。」
豊臣秀吉 “金の辣油”
夢は掴むまであきらめぬ
農民から天下人へ上りつめた“秀吉公の勢い”をイメージ。
奈良漬のコクに白ごま油を合わせた甘口の和風らー油で、 辛さよりも旨味がしっかりと広がる“やみつきの味”。 お漬物グランプリやごはんのお供グランプリなど、 数々の賞を受賞した実力派で、 ごはん、豆腐、ピザ、パスタにも使える万能調味料です。
豊臣秀長 “大和みそ"
静けさに宿る強さ。
「争わずして世を治めた“豊臣の良心”・秀長公。
その温かい統治の象徴である“和をつなぐ力”を、
季節の野菜と奈良漬で仕上げた《大和みそ》に重ねました。
高級仕出しやホテルでも採用される実績ある奈良みそをベースに、秀長公がつくった“和の輪”を現代の食卓へ届ける一品です。
焼きおむすび・おでん・厚揚げに合わせれば、
香ばしさと深いコクがぐっと引き立ち、どんな料理もワンランク上に仕上がります。」
織田信長 “炎の辛みそ”
己の道は、自ら切り拓く
己の道を切り拓いた“革命の武将”・織田信長公をイメージしました。
その恐れを知らぬ烈火の情熱を、《炎の辛みそ》として表現しています。
奈良漬の旨味に奈良県産唐辛子をたっぷり合わせ、
辛さの奥に発酵の甘みと香ばしさが広がる“大人の旨辛”。
肉料理やラーメンなど、攻めの一品として現代の食卓で力を発揮します。
徳川家康 “銀の塩だれ”
待つ力こそ、勝つ力
「長き戦乱を耐え抜いた徳川家康公。]
その“焦らず、おごらず、時を待つ力”を、穏やかな塩だれで表現。
奈良漬の旨味に昆布を合わせたお酢を利かせてあっさりの塩味。
白ごま油の香りと発酵のコクが素材を静かに引き立てます。
サラダチキン、焼き鳥、しゃぶしゃぶ、野菜炒めまで、
幅広く使える“静かな勝者の味”として仕上げています。
時代を超えて愛される、発酵の美味。
Instagramも発信中!←こちらから